Contents 📚 読書をお得に楽しむ方法! 📚 「本を読む時間がない…」「買う前に内容を知りたい…」 ✅ Kindle Unlimited なら 月額980円で200万冊以上が読み放題! 📌 どれが自分に合う?選び方のポイント! 🔹 じっくり読みたいなら → Kindle Unlimited📌 Kindle Unlimited・Audible・flyer の比較表
そんなあなたには 3つの選択肢 があります!
✅ Audible なら プロのナレーションで耳から学べる!
✅ flyer なら 10分で本の要点をサクッと理解!📊 Kindle Unlimited・Audible・flyer 比較表
サービス 特徴 無料体験 料金 📖 Kindle Unlimited 200万冊以上が読み放題 30日間無料 月額¥980 🎧 Audible プロの朗読で耳から読書 30日間無料 月額¥1,500 ✍️ flyer 10分で本の要点を学べる 7日間無料 月額¥550〜
🔹 スキマ時間に聴きたいなら → Audible
🔹 要点だけサクッと知りたいなら → flyer
自己肯定感を上げる
OUTPUT読書術
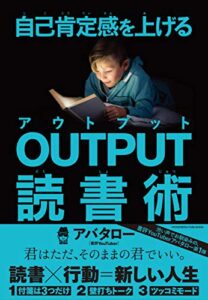
書評YouTuberとして活動されているアバタローさんの書籍第一弾です。
ご本人のOUTPUT術を惜しげもなく書かれている本書。書評される方はもちろんですが、個人的に読書初心者の方にこそ読んでいただきたい一冊となっています。読書のすばらしさや大切さ、読み方やOUTPUTの方法まで丁寧に書いてあります。
本書を読めば、読書の効果を最大限に活かせること間違いなしです。
アバタローさん自身とても苦労をされていて、そんな時に助けてくれたのが読書だったとのこと。
寄り添ってくれるような言葉の数々に、アバタローさんの優しい人柄が伺えるような気がします。
そんなアバタローさんのOUTPUT術を抜粋して紹介していきたいと思いますので、少々お付き合いください。
それではいきましょう!
OUTPUTの原則と基本

OUTPUTの原則
「自分のペースを崩さないこと」ー これがOUTPUT読書術の大原則です。
出典:自己肯定感を上げる OUTPUT読書術
どうしても他人と比較してしまいがちになるのは、人間の性なんでしょう。
自分よりたくさん本を読んでいる人。素敵な発信ができる人。注目を浴びている人。
自分自身、比較してしまい焦ったり不安になったりすることがあります。
SNSのフォロワーの数であったり、いいねの数もそうですし、ブログのPV数を比較してしまう、なんてこともありますよね。
どれだけ成長したか「過去の自分」と比較してあげるのが原則です。
自分の歩幅で発信して、ゆっくりでも一歩ずつ成長していきましょう!
他者からの承認を求めず、楽しむことを考えよう!
OUTPUT読書術の基本骨格
OUTPUT読書術には基本となる骨格が4つあります。
- 準備
- 読解
- 要約
- 発信
この基本が分かれば全体像を掴むことができますので、次に説明するOUTPUT術が理解しやすくなります。
ひとつずつ解説していきます。
準備
いきなり読むことはせず、集中できる環境を作ることです。
とりあえず見えないところにスマホを置くことから始めましょう。
読解
これは話のオチを最初に見てしまうことです。
1ページ目から読み進めていかないといけないというルールは読書にはございませんので、安心してオチを読んでください。
著者の主張を自分なりにもっておくことは、全体像を理解する上でとても大切です。
重要な箇所に線を引いたりメモを残しながら読み進めて!
要約
重要な部分だけを残し、まとめることが要約です。
読み終えた本を振り返ると自身が線を引いた箇所、メモが残っているます。これらをまとめ、自分の言葉へ編集していくことで伝えたい部分が残っていますので次の発信がスムーズになります。
発信
自分用の読書メモ、誰かに本をおすすめする、SNSやブログに投稿する。
自分に合った方法で発信してみましょう。
発信が記憶に定着させる近道。恥ずかしがらずにチャレンジ!
アバタロー式OUTPUT術

この本のメインテーマでもあるOUTPUT術について解説していきたいと思います。
その中でツッコミモードと付箋の役割と枚数について解説していきます。
ツッコミモード
ツッコミと言っても面白い返しというわけではなく、純粋な疑問や気付きを投げかけてあげることです。
どこにどうツッコんでいいのかわかりません!という方に本書にあるツッコミ定番ポイントを3つ紹介していきます。
問い
なぜこの本を書いたのか、何のために書くのか、作者の主張に対してインタビューするような感じでツッコミを入れましょう。
この問いを投げかけてあげると著者がわたしたちに伝えたいメッセージを正しく拾うことができるようになります。
主張
著者の主張に「なぜ?」を突き付けましょう。
自分なりに解釈した著者の主張をもとに違和感があれば対話形式で問いかけていきましょう。
根拠
主張の近くには「なぜなら~」という根拠が存在しています。
その根拠に対してまずは疑いをもっていきましょう。科学的に正しくても自分には当てはまらない。そんなこともあると思いますので、鵜吞みにせずいったん立ち止まるようにしましょう。
以上3つの定番ポイントでした。
このモードで読み進めツッコミを本の中にメモしていくと、要約作業の際に自分の意見が作りやすくなりますのでお試しあれ。
付箋の役割と枚数
わたしは本を読むときに付箋をしていませんでしたが、本書を読んで付箋を活用しようと思いました。
その理由が役割と枚数にあります。ひとつずつ解説していきます。
役割
まず、ペンと付箋それぞれに明確な役割を与えてあげましょう。
それぞれの役割ですが
ペンは「著者」にとって重要な箇所
付箋は「読者(読み手の私たち)」にとって重要な箇所となります。
こうすることで、著者は何を言いたいのか(ペンの箇所)と自分にとって重要な情報(付箋の箇所)を分けてあげることができます。
付箋の枚数
次に付箋の枚数ですが、アバタローさん自身は3枚という制限を設けておられるそうです。
制限を設けることで貼りすぎを防ぎ、自分にとって重要な部分を明確にできます。
最後に、どのような手順で付箋を貼っていくかについてみていきましょう。
step
1本を1章読む。
step
2その中であなたにとって最も重要だと思うページに1枚付箋を貼る
step
3各章でステップ2を行う
step
4貼った付箋を3枚に厳選する
3枚の付箋が残るページが「自分にとって本当に大切なこと」です。
このように自分で選ぶことを「自己決定感」と言うそうです。自己肯定感や幸福度を高めるために自己決定というのはとても重要な要素です。
取捨選択で自己決定感を育もう!
アバタロー式INPUT術

本書にはアバタローさんのINPUT(本の読み方)も紹介されています。
ここも面白いと思いましたので、ふたつ紹介させてください!
本とネットの使い分け
わたしは特に考えていなかったのですが、みなさんは本とネットで情報を集めるときにどのような意識で使い分けていましたか?
アバタローさんおすすめの使い分けは以下の通りです。
本 :正確な知識を体系的に身に付けたい時に使うツール
ネット:断片的な情報を素早く手に入れたい時に使うツール
出典:自己肯定感を上げる OUTPUT読書術
「体系的に身に付ける」というのは、順序立てて網羅して学んでいくという感じです。
本は情報の信頼性、正確性から正しく順序立てて学びたい事柄(人生において大事なテーマ)に使い、ネットは検索性の高さから補足的にすぐ調べたい時などに活用する。といった使い分けおすすめされています。
自分が得たい情報によってツールを使い分けるというのはとても大事だと思います。
それぞれ、メリット・デメリットありますが使い分けを意識してみてはいかがでしょう?
難解な学術書の読み方
いざ読書しようと意気込んだものの「なんじゃ、この本わけわからん。」みたいな状況に陥ったことはありませんか?
こういった難しい本が読めないのは読解力がないからではなく、パターンを知らないからだと本書にはあります。
3つのパターンと対策が書いてあるのですが、今回はテーマが難解な本でも読み進めるようになる攻略法を解説したいと思います!
テーマ自体が難しい本を読むコツ
テーマ自体が難しい本というのは、学問系の本のことです。哲学・経済学・医学など、このあたりの本を読めるとかっこいいですよね。
専門性が高いので、学んだことも予備知識もなく読んでしまうと高い確率で挫折します。
そんな難しい専門書だけど、読みたい本があるという方におすすめなのが、
- 全体構造がわかりやすい本
- 文章が分かりやすい本
- 詳細がわかりやすい本
以上の読みたいテーマに関する本を3種類用意することです。
まず、1番の「全体構造がわかりやすい本」というのは図解書など初心者向けの大まかな概要を説明してくれる本です。
2番の「文章が分かりやすい本」というのは文章自体がわかりやすく理解のしやすい本です。解説本や漫画版なんかがいいかもしれませんね。
最後の「詳細が分かりやすい本」というのは辞書のように使える情報量の多い本です。詳しく書いてあればあるほどいいです。
個人的には「全体構造がわかりやすい本」か「文章がわかりやすい本」を読んでみて原書を読むぐらいでもいいのかな?と思います。さらに知りたいことやわからないことがあれば「詳細がわかりやすい本」を追加する。といった使い方でしょうか。
段階を踏みすぎると、わかったような気になって最初に読みたいと思った本を読まなくなる気がしちゃうので。
他にも背景知識を知らないパターン、文章自体が難しいパターンといった本の対策も書いてありますので気になった方はぜひ本書で確認してみてください。
Kindle Unlimitedではさまざまな図解書が読み放題なのでおすすめです。
少し興味があったので古事記と聖書は読みました。意外と面白いですよ!難解な本の入り口にどうぞ!
まとめ
今回はアバタローさんの書いた「自己肯定感を上げるOUTPUT読書術」をもとに
OUTPUTの原則と基本
原則は自分のペースを崩さないこと。4つの基本骨格「準備・読解・要約・発信」について。
OUTPUT術
ツッコミモードで問い・主張・根拠に「なぜ?」。付箋の役割と枚数を明確に自己決定感を育む。
INPUT術
本は体系的に、ネットは補足的に使い分ける。難解な本を読むコツは図解書から。
について解説してきました。
この本を参考にわたしのOUTPUT力も高めていきたいと思います。皆さんも一緒に楽しい読書ライフを送ってみませんか?
まだまだ紹介しきれていないところが大いにありますので、少しでも気になったという方は是非読んでみてください!
エピローグのアバタローさんと恩師のエピソードはとても良かったです。
この記事が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!


